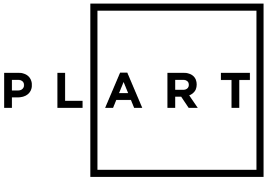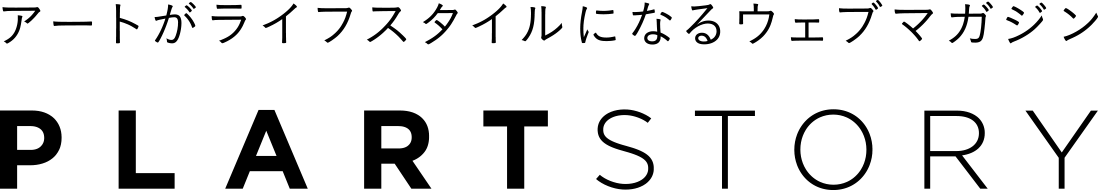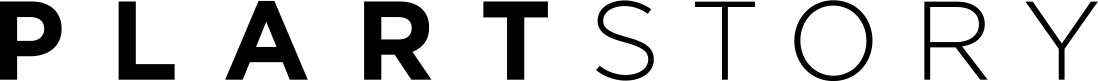ポストヒューマンへの手がかりとしてのメディア・アート 【多摩美術大学 教授 /アーティスト 久保田晃弘】


4月15日号
「メディア・アート」と聞くと、アートに関わっている人には難解に、テクノロジーに関わっている人には奇異に感じるかもしれない。テクノロジーと文化の多様性が進む今、わたしたちは次々と生み出されるメディア・アート作品の行方を、どのように見つめ考えていけば良いのだろうか。
東京大学工学系研究科で船舶工学と流体力学を学び、人工物工学研究センターの教員を務めたのちに、多摩美術大学(以下:多摩美)のメディア芸術コースで教鞭を取る久保田晃弘(くぼたあきひろ、以下久保田さん)さんに伺った。
パーソナル・メディアで宇宙とつながる
プログラムコードをその場で組み立てたり変更しながら音楽を奏でるライヴコーディング・パフォーマンスを行なったり、生物学、遺伝子工学の発展による生命概念の変容そのものを芸術表現にするバイオ・アートをいち早く多摩美の授業に取り入れたりと、「メディア・アート」のカテゴリを自身の手で拡げ続ける久保田さんだが、その代表的なもののひとつ、衛星芸術プロジェクト「ARTSAT」を始めたのは2010年、50歳のときだった。
プロジェクトは、これまでに10cm角の立方体の衛星「INVADOR」と螺旋を描いた彫刻的な衛星「DESPATCH」の二機を宇宙に打ち上げ、いずれもエクストラ・サクセス(ミッションの達成度を4段階に分けた中でも最高の達成である言葉。ミニマムサクセス、ミッションサクセス、フルサクセス、エクストラサクセスがある)を達成した。
INVADOR promotion video from ARTSAT on Vimeo, directed by Tsushima Takahiro.
DESPATCH promotion video from ARTSAT on Vimeo, directed by Tsushima Takahiro.
ARTSATプロジェクトのひとつの目的は、パーソナル・メディアとしての衛星の可能性を探ること。地球から芸術メディアとしての衛星を打ち上げ、地上と電波を通じてコマンドやデータをやり取りすることで、衛星や宇宙と直接繋がることができる。
「宇宙をパーソナル・メディアで拓きたいと思ったんです。自分の部屋からコマンドを衛星に送ると、衛星から音や詩が返ってきたり、自分が書いたコードを宇宙で実行してくれる距離感というか感覚でしょうか。衛星が地球を周回している間は、毎日必ず2〜3回は衛星の運用(通信)をしなければなりません。そうすると、その時間に合わせて生活リズムが決まってくるんですよ。ハイビジョンで宇宙飛行士と話をするようなすごいイベントではありませんが、毎日の掃除や洗濯と近い感覚で宇宙と関われるわけです」
「パーソナルになる」「日常の中にメディアを持ち込む」ということが、ケとハレの二者択一的な選択肢から抜け出し、別の道を作ることにつながるという。

「ARTSATも最初は衛星からのデータで何か面白いことができないかなぁ、というくらいの気持ちでした。僕は、どんなメディアも、それがパーソナルになる時が面白い、と思っています。“新しいものを生み出す”とよく言いますが、新しいものができた直後ってあまり面白くないんですね。メディアそのものの価格が高いし、使える数も少なくて、まだ研究者の手の中にある。お金がかかるものは失敗できないから、真面目で保守的なことしかできません。でも芸術の側から見ると、それでは面白くないと思うわけです」
久保田さんは衛星で展開するアートもまた「メディア・アート」の延長であると考えている。そのメディアとしての小型衛星が、自分たちのチームに属するのではなく、オープンに一般人たちの手に渡っていくことこそがアート活動である、とイメージをしているようだ。
「パーソナルというのは、それぞれの人が与えられたものではない方法を考えられるようになることです。例えば、スマートフォンのOSはAppleのiOSとGoogleのAndroidの2つが大きなシェアを占めていますが、それ以外の選択肢を考えられることが重要で、「この道しかない」と言われることがディストピア(理想郷/ユートピアの反意語)の世界だと思うのです」
クラシックやロック、ジャズに触れながら過ごした学生時代
久保田さんの作品には工学と芸術が密接に交わっている。異なる分野をまたいで作品を生み出せる理由を知るために、まずは久保田さんの少年時代を伺った。すると、音楽に幼少から親しんでいたという答えが返ってきた。音楽とひと言でいっても、久保田さんが関わってきたジャンルは多様だ。
「母の勧めで5歳の時にピアノを習い始めました。ピアノの先生が隣に住んでいて、練習したかどうかが一目瞭然わかってしまうので、真面目にやらざるを得ませんでした(笑)。でも小学校の高学年になると、他の子達が放課後遊びに行くのに自分だけ習い事っていうのも恥ずかしくなって、ピアノを習いに行くのはそこでやめてしまいました。今思うと、もったいないことでしたが」

中学生の時に親しんだのはロック。特に、KING CRIMSON(キング・クリムゾン/イングランド出身のプログレッシブ・ロックバンド)やHENRY COW(ヘンリー・カウ/イギリスのアヴァンギャルド・ロック・グループ)のようなイギリスのプログレッシブ・ロックやNEU!(ノイ/ドイツのプログレッシブ・ロック・バンド)やCAN(カン/ドイツのクラウト・ロック・バンド)のようなドイツロックについて、友人と良く議論していた。『ミュージック・ライフ』※1や『音楽専科』が出版されていた時代だ。
なかでも印象に残っているのは、中学校の音楽の先生だったという。
「リベラルな、変わった先生でした。モーツァルトやベートーベンのような、いわゆるクラシック音楽を教えるのはつまらないと言って、『印象派とはこれです』と天井に映ったプールの照り返しを指差したり、『ストラヴィンスキー(ロシアの作曲家、指揮者、ピアニスト)は兵士の音楽だ』と言って変拍子のリズムを聞かせてくれる。音楽室に遊びに行くと、トランペットやサックスなど色々な楽器に触らせてくれるんですよ。ある日、Jon Lord(ジョン・ロード/Deep Purpleのキーボード)の「Space Truckin’」※2のソロのコピーを弾いていたら、『そういうの弾くんだったらジャズのほうが面白いよ』とジャズを勧められたり(笑)」
高校では、新入生歓迎会のコンサートでMiles Davis(マイルズ・デイビス/アメリカのトランペット奏者)の『AGHARTA(アガルタ)』※3が演奏されて、ジャズ研に入った。
高校の時はEric Dolphy(エリック・ドルフィー/アメリカのジャズ・マルチ・プレイヤー)やAnthony Braxton(アンソニー・ブラクストン/アメリカのジャズ奏者・作曲家)、そして78年に初来日した「DEREK BEILEY(デレク・ベイリー/イギリスのギター奏者)の演奏を聞いて、ヨーロッパのFREE IMPROVISATION(フリー・インプロヴィゼーション)にどっぷりはまりました。STEVE LACY(スティーヴ・レイシー/アメリカのサックス奏者)や日本のEEU(Evolutional Ensamble Unity/高木元輝、近藤等則、吉田盛雄の3人からなるフリージャズグループ)など、70年代の終わりから80年代くらいにかけての即興音楽は、とても面白い時代でした。もちろん周囲は、Bill Evans(ビル・エヴァンス/アメリカのジャズピアニスト)やChick Corea(チック・コリア/アメリカのジャズピアニスト)のような、整ったジャズが全盛だったのですが、なんかそこにはハマれませんでした(笑)」
ピアノからロック、そしてフリージャズという音楽のカテゴリを飛び越えて、久保田さんのこれまでには、常に「音・音楽」が存在していたことがわかる。
またお話を聞いていく中でも、音楽の作り手たちのさまざまな名前が飛び交い、久保田さん自身が音楽に触れて自分が音を鳴らすことに傾倒しながらも、それに関わる人たちを客観的に見つめ、音楽への評論や批評を仲間としていたことも伺える。
自分自身が楽しむ音への探求と、それを作り出すアーティストへの視線の土台は、いま現在多岐に渡るメディア・アートを作り出す自分自身の研究と、それを評する立場であることと重なる。
※1 主に洋楽を扱っていた雑誌。1998年に休刊。その後、アプリ「MUSIC LIFE plus」として再刊。
※2 「スペース・トラッキン」Deep Purple(ディープ・パープル)のアルバム「ライヴ・イン・ジャパン」収録。ジョン・ロードの見せ場が多い名曲。
※3 1975年に日本公演を収録してリリースされたアルバム。ジャケットは現代作家の横尾忠則が担当。
音楽と工学。その2つをわけないという選択
久保田さんが音楽と共に子どものころからもうひとつ深く関わっていたものが工作や科学だった。パーソナル・コンピュータが登場し、情報機器にも大きな変化があった70年代後半から80年代に学生時代を過ごした。
「小学校のときはラジオはまだ真空管で、誠文堂新光社などが自作DIYラジオや、ホビー工作用のキットを売っていました。中学になるとそれはトランジスタになり、高校になるとICに代わり、大学に入ってからはマイクロ・コンピュータが登場しました」

秋葉原がまだラジオの街だった頃。18歳で大学に入学する少し前にNECの「TK-80」が登場し、24歳の時には「Macintosh/マッキントッシュ」が発売された。1960年生まれの久保田さんから見ればスティーブ・ジョブズは5歳上になる。さまざまな形でに起こった技術革新の推移と共に成長した世代でもある。
大学では工学の道へ進んだが、並行してジャズの演奏活動も続けていた。
「工学は本業で音楽が趣味みたいな感じですが、当時はそういう二足のわらじがいいと思っていたんです」と久保田さん。
ジャズの演奏活動でも、学内だけでなく、他の大学のメンバーなど外との交流が広がっていた。さらに、大学院の在籍中は、ジャズ誌など音楽雑誌の記事も取材、執筆するようになったという。
「今でいうところの分人みたいな話ですが、ある時、分人には限界があることに気がつきました。趣味と本業を分けることの限界に気づくと、だんだんともっとその先にまで行きたいと思うようになりました。何事にも自分のその時々の全能力を傾けて取り組みたい。だから最終的には自分を分けたくなくなるんですよね」
1983年、電子楽器で世界初のフルデジタルシンセサイザー「DX7」がヤマハから発売された。それから14年が経ち、マッキントッシュの「パワーブックG3」(1997年)が登場し、汎用のラップトップによるソフトウェア・シンセサイザーだけでライブ・パフォーマンスが出来るようになった。

2009年5月、英国ニューカッスル大学カルチャーラボにおける、自作Arduinoギター+ライブコーディングによるライブ・パフォーマンスの様子。スクリーンには手元の動きのオプティカルフローによって流動するノイズが投影されている。(画像久保田さん提供)
「DSP(Digital Signal Processor/コンピュータによる音響合成技術)が個人レベルで扱えるようになって、それまで離れていたエンジニアリングのスキルと音楽のスキルが直接結びつけられるようになりました。音楽と工学を区別せずに一緒にできるのではないか、と考えるようになった時に、多摩美でデジタルメディアをベースにした学科を新しく立ち上げる、という声がかかったのが1998年。それからあっという間に20年が経ちました」
音楽と工学を分けずに取り組むことを、自分自身の手で、常に挑戦し行動し続けたことで、久保田さん自身が想像もしていなかった場所に流れ着いた。
メディア・アートの本質とこの先の人類に必要なこと
久保田さんは、学芸員の畠中実さんとの対談を軸とした書籍『メディア・アート言論』(フィルムアート社)を2018年3月に上梓している。その書籍は、メディア・アートを3つの年代に分けて捉え直し、さらに最新テクノロジーとアートの新たな邂逅によるバイオアートなどについても触れている。

久保田さん自身が定義する「メディア・アート」とは何か、改めて伺った。
「……この本で考えたかったことは、つまりは『ファイン』メディア・アートと言えるものでしょうか。ファッションにおけるモードといってもいいかもしれません。だとすれば、ファインアートにおける思想や哲学、美術史や美学に相当するものは何なのか。メディア・アートには広告やエンターテイメントも含まれるのかもしれませんが、アートと呼び得るためには“ここが原点だ”といえるものが必要で、それがないままメディア・アートという言葉だけがインフレーションしてしまえば、あとは政治や経済と同じパワーゲームになってしまいます。メディア・アートを、今日のGAFA(Google、Amazon、Facebook、Appleの頭文字)的大企業が日々繰り広げる資本主義のゲームと区別することが大切だと思っています」
宇宙に車を送り込んだElon Musk(イーロン・マスク/南アフリカ出身、アメリカの実業家・投資家。TESLAのCEO)の成果も、「優れたエンジニアリングの賜物」で、それは彼らが販売しているテスラ(電気自動車)の見事な宣伝ビジネスの場にもなっている。
メディア・アートにとっては、どんなに予算や技術があっても実現できないイマジネーションとそれを支える思想を持てるのかが大切なのかもしれない。
「もうひとつ重要なのはバランスです」と久保田さん。
「最近のメディア・アート関連のワークショップやレクチャーで、『メディア・アートのためのプログラミング講座』や『メディア・アートに役立つ電子工作入門』などは良く見かけますが、『メディア・アートのための美学講座』や『メディア・アートのための美術史』は全くと言っていい程ありません。
しっかりしたエンジニアリングの基礎を持っている人が、技術史や技術倫理だけでなく、美学や美術史も同じように学ぶことが必要だと思っています。今は『メディア』と言えばソフトウェアを指す時代です。だから『メディア・アートのための美学講座』や『美術史講座』を通じて、ソフトウェアの美学やメディアの美術史を一緒に考えていきましょう、と僕は提案したいのです」
テクノロジーの進化や変化はどんどん速くなっているように見える。最近ではAIが書いた絵がアートコレクターに買われた、という話もあるが、そうした時代に必要な価値観とはどんなものなのだろう。
「ここ数年、人間に依拠しない芸術を人間がどこまで想像することができるのか、ということを考えています。人間に依拠しない芸術に対して、僕らは沈黙するしかないのかどうか」

「そうすることで、僕らはポストヒューマン(人間の次なるもの、人間を超えたもの)になれるかもしれません」
久保田さんは「スペキュラティブ・デザイン」についても言及している。現在の延長線上にある未来だけを見るのではなく、他にも存在し得る「可能な」未来の姿を提示し、それぞれの世界(の違い)に対する議論を重ねて行くデザインの方法論だ。
「ポストヒューマンのあり方というものを僕らがどうやって考えて行けばいいのか。議論することや問いかけることそのものが、美術だけでなく社会全体にとってもますます重要になっています。スペキュレーション(思索)自体が美術の役割や社会の価値になっている」
コンセプチュアル・アートの先駆けとなったマルセル・デュシャン以降の美術にとって重要なのは、もはや感性としての「美」ではなく、理性としての「思想」であり、気づいていないことを問いかけるための手段のひとつにもなった。
「2002年に松井みどりさん(日本の美術評論家/多摩美術大学芸術学科非常勤講師)が『アート:“芸術”が終わったあとの“アート”』という本を出しました。そこに詳しく書かれているように、ポストモダン以降、美術の価値は美とは直接関係しなくなりました。僕自身は、アートの本質は、自然言語だけを使わない哲学であると思っています。
哲学者は言葉を使いますが、アートは同じことを他の形式や方法でも表現します。それはもちろん色でもいいし形でもいいし動きでもいい。“ありとあらゆる形式を駆使した思想や哲学”が、今日のアートの意義なのではないかと思っています」
これからは、美術にかぎらず私たち全員が常に問いかけ、あらゆるものに寛容さを持ちながら、深く思索して生きていく必要があるのだろう。
インタビュー中、久保田さんはにこやかに「学生にはキャリアデザインはしなくてもいいと言っているんです」と話してくれた。

「大学に限らず『キャリアデザイン』をしましょう、と良く言われますが、少なくとも10年スパンでものごとを考えて、それを予測しようとしたことはなくて、目の前のことを一生懸命、というか120%やろうと心がけているうちに、いつの間にかこんなところに来てしまった、という感じでしょうか」
曖昧さを抱え、決めながら動き続けることが大事、とも教えてくれた。
先がわからないだけに勇気がいることかもしれない。
でも自分に対する哲学があれば、それでもきっと大丈夫だ。
kakite : Asami Matsumoto / photo by Mika Hashimoto / Edit by Chihiro Unno

久保田晃弘 / Akihiro Kubota
多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース教授。芸術衛星1号機の「ARTSAT1:INVADER」でアルス・エレクトロニカ 2015 ハイブリッド・アート部門優秀賞をチーム受賞。 「ARTSATプロジェクト」の成果で、第66回芸術選奨の文部科学大臣賞(メディア芸術部門)。近著に「遙かなる他者のためのデザインー久保田晃弘の思索と実装」(BNN新社, 2017)「メディアアート原論」(フィルムアート社, 2018)がある。がある。http://hemokosa.com
取材フォトギャラリー