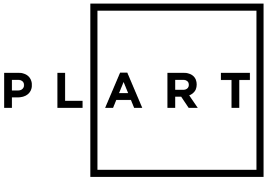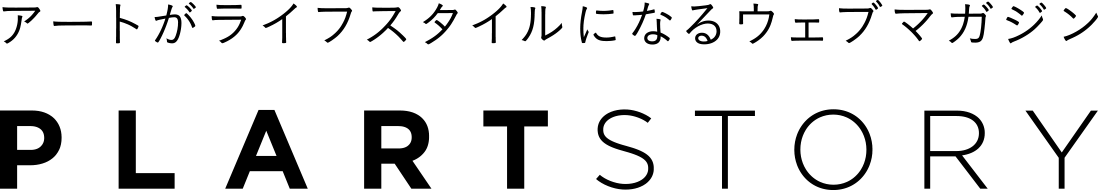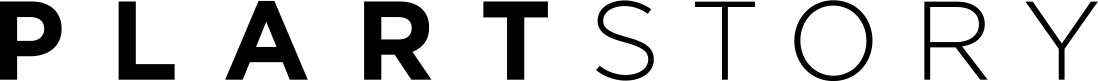【連載】アートとビジネス vol.7「アートは型を揺さぶり包摂をつくる」株式会社ロフトワーク代表 林千晶


11月15日号
連載「アートとビジネス」とは?
昔から、あこがれのビジネスマンには、アート好きな人が多かった。
その共通点はなんだろう?
それは、「人と違う視点を持っていること」ではなかろうか。
ゼロから生まれてくるアートが好きで、そして、自分も新しい価値を創る。
未開拓のシーンに挑戦するビジネスマンに憧れを持ち、少しでも近づきたくて、僕らは働く。
その人にはなれないけど、アートを通して同じ視点を取り入れる事は出来るかも?
アートには「新しい価値を生み出すヒント」がきっと、あるから。
渋谷駅から道玄坂を上り、首都高の高架が見えてきたところで視線を左に移すと、あるオフィスビルの袖看板が目を引く。通常はテナント名が羅列されるスペースに、数フロア分の枠を縦断するポップアート。社名の表示はないが、ポップアートが専有しているフロアに、株式会社ロフトワークのオフィスが入る。
同社の共同創業者であり、代表取締役を務めるのが林千晶(はやしちあき)さん。
ロフトワークは、Webコンテンツや映像、サービス、コミュニケーション、空間に至るまで幅広い領域のデザインを手掛けるクリエイティブエージェンシーだ。2000年の創業以来、“社内にクリエイターを抱えない体制とオープンコラボレーション”というスタイルを貫いている。
ビルの1階では3Dプリンターやレーザーカッターが使えるモノづくりカフェ「FabCafe」を運営。エレベーターホールやオフィスには、淺井 裕介さんやBenjamin I. Outram、谷口悦子さんの作品が展示され、林さん自身は、2016年の「KENPOKU ART 2016 茨城県北芸術祭」でコミュニケーションディレクターを務めている。
そこで林さんに「アートがお好きですか?」と尋ねたら「大好き!」と身をのり出して答えてくれた。しかし30分後には「買われることだけを意図したアートはつまらない」という発言も飛び出した。
インタビューから見えてきた、林さんが考える「アートがビジネスにくれるもの」とは?
私は私の意思で私になった
アラブ首長国連邦出身。早稲田大学商学部ではマーケティング研究で知られる恩藏直人教授のゼミで学んだ。卒業後は花王に入社。その後、アメリカ・ボストン大学院でジャーナリズムを研究。帰国後は、日本で「クリエイティブ・コモンズ」(作者の著作権を保持したまま、作品を自由に流通させるためのプロジェクト。インターネット普及の流れを受けて誕生した)の普及活動に尽力。時を同じくして、ロフトワークを設立する。
アラブ首長国連邦は、7つの首長国からなる。その政治的中心地アブダビで、林さんは6歳からの約5年間を過ごしたという。
話の糸口に、アブダビでどのように育ったのかを訊ねると、林さんは「私はそれを、ずっと否定して生きてきた」と答えた。
「人って、人との差を見つけて『だからあの人はこうなんだ』って紐づけることが多いですよね。たとえば『林さんはアブダビで育った。だからユニークなんだ』とか。でも私が私なのは、アブダビで育ったからではない。私がこう生きたいと思って生きているから私になっているんです。今の自分らしさの大半は、幼少期の体験よりも、大学を卒業するころから作られ始めたと思っています」
「基本的にはそう考えています」と強調した後、「とはいえアブダビの影響がないわけではないよね。最近はそこをちょっとは認めてもいいかなって思うようになりました」と笑顔で言い添えた。
アブアビでは1日に5回、街のモスクから礼拝を呼びかける「アザーン」が流れた。土に額をつけ祈りを捧げる人たちを見ながら専用車に乗り、小学校へ通った。肌の露出を禁じる文化だから、日本人の感覚では標準的な服装さえ批難の対象となり得る。子供同士でも万が一、身分が高い家の子を怪我させることがあれば、日本人でさえ命の保証はない。
林さんは、当時の母親の言葉を思い出す。
「現地の人たちのルールを分かっていないんだから、現地の人と交わってはだめよ」
差別感情からではなく、日本人のルールが適用されない文化の中で身を守るための忠告だった。
「王族がいる。一方では、ある意味人間以下の扱いを受ける人もいる。人間の価値さえ絶対ではない。絶対だと思っていた“正義”や“悪”も、ルールが変われば変わることがある。そういったことを本能的に知ったし、知っておきたいという気持ちも生まれた。そこにはアブダビに住んでいた影響があるかもしれない」
林さんは「今の自分の大半は、大学卒業くらいから始まった」との言葉どおり、就職活動では「何もできないけれど、それではだめですか?」というスタンスを通した。バブル好景気が崩壊した直後だったが、花王株式会社へ就職した。
興味があったのは、いつも「生き方」
花王の総合職で社会人生活をスタートさせた林さんは、化粧品開発というモノづくりに関わりながらも「もうモノで満たされる時代ではない。これからは『モノを解釈する価値観』の時代ではないだろうか」と考えた。
「当時から、女の人たちの中には『凛とした自分』への憧れがありました。流れに歯向かうのではなくて、しなやかに受け止めながら、ぶれない自分でありたい。そういう生き方への憧れは今でもあると思っています」

『凛とした、しなやかな自分』を考えたとき、肩パット入りの洋服は「しなやかさを消してしまう」と違和感を抱いた。時代はマットなメイクの全盛期。落ちない、崩れないことが重要視される中、「落ちないとか崩れないとか後まわしでいい。女性の肌は輝いていないと意味がない。活き活きと瑞々しく輝くようにしてください」と開発チームに頼んだりもした。
モノづくりを通し「人の生き方」「人の輝かせ方」を模索してきた林さんが、その後、渡米し「働き方」を研究、情報を発信するジャーナリズムの道を進んだのも、自然な流れと言えるだろう。
安易な自己肯定で失うもの
インタビューはオフィスビルの最上階で行われ、窓の外には渋谷の空を見渡すことができた。白い雲の向こうに太陽を感じさせる明るい空を背景に、林さんは質問に答えてくれる。柔らかい言葉つき、今のために言葉を選んでくれたような切り返し。「凛とした自分」のお手本のようだと思った矢先、ふと林さんは声を沈ませた。聞けば最近プライベートで、思考の型について思うことがあったという。
「自分の思考パターンって破れないよね。ダメだったことは悪かったってちゃんと自分で反省しないと、また同じプロセスに落ちちゃう。自分に優しくしてくれる人に貢ぎ続けちゃう人っているでしょ? あ、私が貢いだんじゃなく例えばの話(笑)」
空気を和ませながら、一時SNSで話題になったホストとホストに貢ぐ女性客の対談記事を引き合いに思考プロセスの話を始めた。
「その女の人はOLを辞めて風俗に職を変えてまで歌舞伎町のホストに何千万も貢いでいる。対談の内容が本当なら、そのホストはその女性に対して明らかに不誠実だし、彼女は不幸な状況。でも彼女は貢ぐ行為をやめる気はないし、過去の自分の行為にも価値があったと思っている。それは過去の自分の判断を、否定したくないからだよね」
「今まで『あの時の自分はダメだったが、それも含めて自分だ』と思うことが悪いとは思っていなかった。でもちゃんと自分で『悪かった』と思わないと、ダメだったときの型を何度でも使ってしまうんだよね。パチンコ台にも玉が流れやすいルートがあるのと同じイメージ。いくつ玉を通しても結局いつも同じところに落ちてしまう。人間の思考も脳内の電気信号だから、同じ回路ばかり使っていると、そこの電気が通りやすくなるんじゃないかな」
そこを揺さぶるのがアートじゃない?
パターン化には、効率化を図り失敗のリスクを減らす等の強みもある。それを認めた上で林さんが危惧するのは、本来は違うルートで考えるべきことも、無自覚のうちに強引に得意なルートで処理するようになることだった。
「型が強くなりすぎると、どんなインプットがあっても『前に使ったあのプロセスでいこう』とつい考えてしまう。本当はもっと色んな解釈や作り方があり、別のプロセスを選べばもっと豊かなアウトプットが生まれたかもしれない。そのアウトプットならば次の誰かのインプットになったかもしれない。もっとたくさんの人とも関われたかもしれない。いつものプロセスで、いつも同じように『いいね』といわれるような、単純なアウトプットしか出せなかったら、他の人にとっての魅力的なインプットにもならない」
どんな物事にも、インプット、ツールと技法、アウトプットの3つのプロセスがある。3つそれぞれに無数の選択肢があり、組み合わせの分だけ可能性がある。自分の思考が型にはまってしまっていないかを自覚するにはどうしたらいいのだろうか。ここに林さんは、アートの存在価値を認める。
「他者の強いアウトプットに驚き、自分の考え方の短絡さに気づき、プロセスが変われば一番面白い。その揺さぶりをかけるのがアートじゃない?」
自分の思考回路が恥ずかしくなるようなアート体験を
思考プロセスには、強みと弱みがある。それを知った上で自分のプロセスが型にはまっていないか省みることが大事。この点は、ビジネスの場に置き換えても通じるだろう。では「ロジカルに説明できるものしか認めない」というタイプの人にも、アートの揺さぶる力は通用するのだろうか。
「よほど強烈なアウトプットに触れれば、『なぜこうなるの?』とやはり理解したくなるはず。その意味で私は、買われることだけを意図したアートは嫌なの。この作品は100万円の価値があるなと金額換算したり、より高く売れるか勘定したり。そういう損得のループを回し続ける典型的なビジネスのプロセスの中でアートを観たり買ったりしている内は、本当のアートとの触れ合いにはなっていないと思う」
「アートには、例えば社会の差別をテーマに“ない”ことにされているものを“ある”と浮き彫りにする力もあれば、キレイとされるものの汚さ、汚いとされるものの美しさを表現する力もある。ビジネスでさんざん使ってきた『損得』の回路に疑いを持ち、それまでの自分の回路が恥ずかしくなるようなアート体験がいいな」
世界は多様。もともと多様。
林さんは今、週1回の代官山ロータリークラブで「会って挨拶するだけでどこまで仲良くなれるか試している」と冗談交じりに明かした。それは遊び心だけによるものではなく、包摂(インクルージョン)の成果を確かめるための実験だ。
「多様性を尊重しようと言われることがあるけれど、『しよう』と言われなくても世界はもともと多様なんだよね。解決しないといけないのは、すでにある多様な要素がそれぞれ分断されて存在していること。交じりあっていないから、お互いが顔を会わせた時にけん制したり批難したり、自分たちの正義を押し付けるような事態が起きてしまう。つまり社会に欠けているのは、包摂なんじゃないかな」
多様な価値観をいかに包摂するか。林さんはそれをずっと問い続けてきた。そして挨拶とアートのちからに希望を感じている。
「やり方で言えば、議論とかワークショップとか色々あるけれど、包摂はもっと物体的で、行動的なアプローチから作られる気がするの。まず会え! 視界にうつれ! みたいな(笑)。実際、ロータリークラブでは週1回の挨拶ですっごく仲良くなってるし、どんな人も10回『おはよう』っていえば、愛せるようになる気がするんだよね」
「反対に、『他の価値観を認めるべきだ』とか『多様性を尊重しましょう』みたいな義務的な取り組みに効力は感じない。ここでも、揺さぶりをかけてくれるのはアートかもしれないね。義務としてではなく、きれいだったり格好良かったり、目を奪われるような一定の美的強度をもって揺さぶってくれる。そういう力のあるアートを支援し、その活動の一部に自分もどんどん関わっていけたらいいなと思っています」
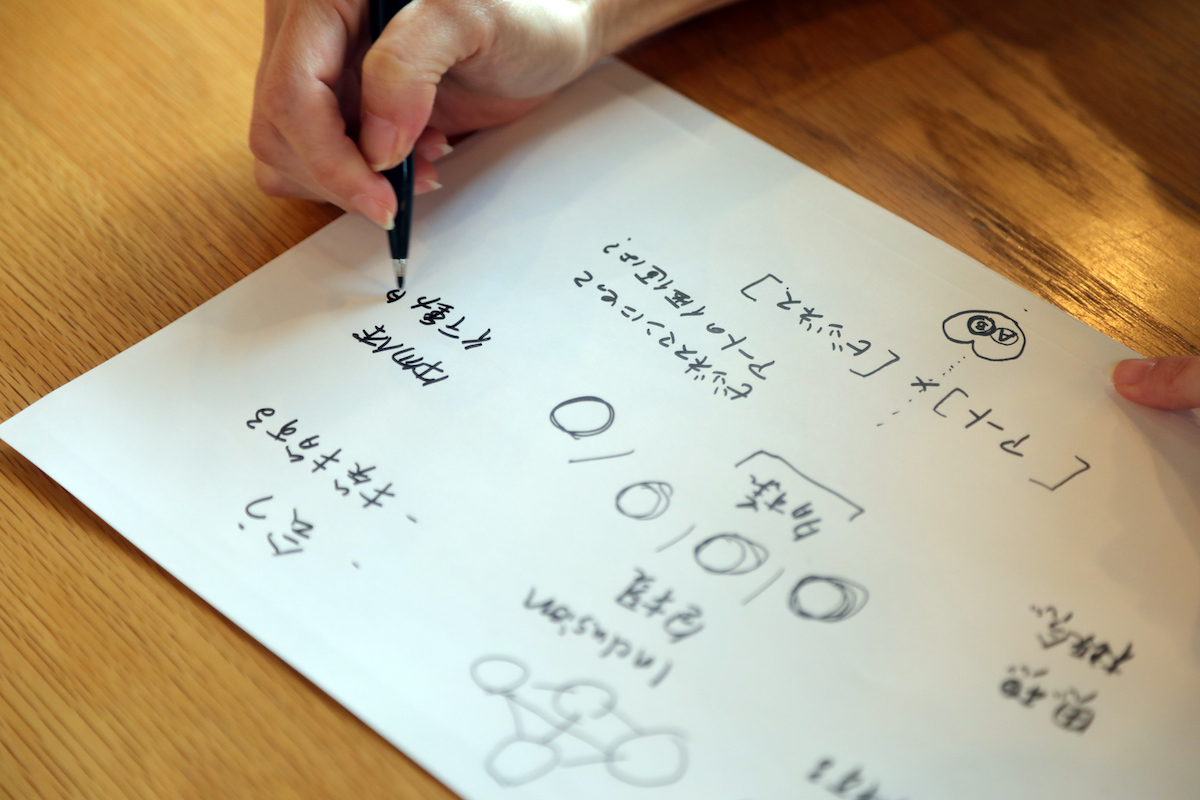
kakite : 塚田史香/photo by 花坊/ EDIT by 松本麻美

林千晶/Chiaki Hayashi
株式会社ロフトワーク 代表取締役
早稲田大学商学部、ボストン大学大学院ジャーナリズム学科卒。花王を経て、2000年にロフトワークを起業。Webデザイン、ビジネスデザイン、コミュニティデザイン、空間デザインなど、手がけるプロジェクトは年間200件を超える。 書籍『シェアをデザインする』『Webプロジェクトマネジメント標準』『グローバル・プロジェクトマネジメント』などを執筆。 2万人のクリエイターが登録するオンラインコミュニティ「ロフトワークドットコム」、グローバルに展開するデジタルものづくりカフェ「FabCafe」、クリエイティブな学びを加速するプラットフォーム「OpenCU」を運営。 MITメディアラボ 所長補佐(2012年〜)、グッドデザイン審査委員(2013年〜)、経済産業省 産業構造審議会製造産業分科会委員(2014年〜)も務める。森林再生とものづくりを通じて地域産業創出を目指す官民共同事業体「株式会社飛騨の森でクマは踊る(通称:ヒダクマ)」を岐阜県飛騨市に設立、代表取締役社長に就任(2015年4月〜)。「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2017」(日経WOMAN)を受賞。
取材フォトギャラリー