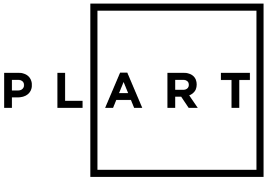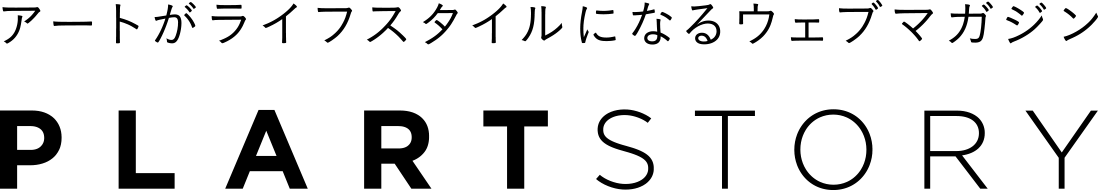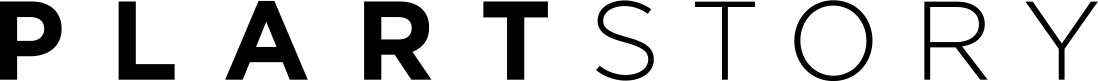「何もないところに劇場をつくりたい」ファッションで日常を揺さぶる【企画・プロデュース 金森香】


9月15日号
「この秋は、どんな服を着ようかな」
季節が変わると、ファッションのことを考えたくなる。新しい服を買うとワクワクするし、雑誌を見ながらコーディネートをつくるのも楽しい。
でも、いくらおしゃれやファッションが好きでも、「服を着るという行為」自体をいちいち意識する人はあまりいないのではないか。
そんな中、「服を身にまとう」意味を、否応なく意識させてくれる人がいる。
ファッションブランド「シアタープロダクツ」では、デザイナーらと共にパッチワークでつなげた布から型紙で切り取って服をつくるワークショップを企画したり、船の上でファッションショーをしたり、障がいを持つ人に合った服をつくったりと、ファッションにまつわる企画を手がける、シアタープロダクツ創業メンバー/現在NPO法人ドリフターズ・インターナショナル(以下ドリフターズ・インターナショナル)理事の、金森香(かなもりかお)(以下金森さん)だ。
ファッションを用いて、「何もないところに劇場をつくりたい」、何度もそう話す金森さん。
一方で、「ファッションはアートではない」とも断言する。
一体どういうことだろう。彼女の考えにじっくり向き合った。

日常と物語のどっちに属しているのかわからなくなった
「まだまだアンダーグラウンドな時代の劇団四季で父は舞台装置のデザインを、母は制作をしているという演劇一家でした。小さい頃から劇団の稽古場に一緒に行ったり、合宿に連れて行ってもらったりとにかく身近に演劇がありました。
5歳くらいのとき、いつも遊んでくれた劇団のお姉さんが主演する、『人魚姫』を見に行ったんです。劇が終わり、カーテンコールで彼女が衣装のまま客席に降りて来たとき、物語と現実の人物が重なりあって、お姉さんが日常と物語のどっちに属しているのかよくわからなくなり、びっくりしたのですが、そのときの衝撃が、私の原体験になったのです」
金森さんは、そんな経験があって、その後たくさんの観劇に足を運んだ。しかし、役者の演技や戯曲には興味がわかなかったと言う。
「演劇そのものよりも、劇が終わる瞬間、物語が舞台から日常に侵食してくる場所の方に興味があると高校生くらいの時に気づいたんです。するとパフォーマンスアートなどにも興味がわいてきて、演劇も観れて実験的な芸術やコンセプチュアルアートにも接することができるロンドンに留学しました」

演劇、アート、そしてファッションへ
金森さんがファッションと出会ったのも、留学先のロンドンの芸術大学としても知られているセントラル・セント・マーチンズだった。
当時のロンドンはDamien Hirst(ダミアン・ハースト)やJulian Opie(ジュリアン・オピー)などがアートシーンを印象付け、現代芸術が盛り上がりパフォーマンスアートなど実験的なことが街のそこここでなされていて、金森さんも大いに刺激を受けたようだ。
「アートの文脈から演劇を見直したり、ファッション科の友人が手がけるプロジェクトを手伝ううちに、ファッションが、今まで自分が関心を持っていた、演劇やパフォーマンスアートといった身体芸術の延長線上にあることに気がついたんです。
コンセプチュアルアートを理解するには、ヨーロッパ史やアートの歴史や文脈をわかっていなければなりませんでいたが、一方、洋服は『かわいい』とか『着てみたい』という、シンプルな欲望に直結しているのも魅力でした。服は身にまとっているうちに、日常のいろんな気づきを生んでいくんじゃないか。そういうアートとはまた違った、穏やかな革命みたいなところがすごく好きになりました」

共鳴するデザイナーと出会い、ファッションの会社を始める
帰国後は出版社に勤めながら、その出版社がもつギャラリーでイベントを企画・運営したり、並行して街でリサーチをする日々。まだ紹介されていないアーティストやクリエイターとの出会いを探していた。その中で出会ったのが、後にシアタープロダクツというファッション会社を共につくることになる、二人のデザイナーだ。

(読むお店 SHOP Of words THEATRE PRODUCTS 伊勢丹新宿店より)
「出会いは、二人が手がけていた『タンプトック展』というイベントでした。一枚のパッチワークの布を、自分の好きなところで切って、その場で縫ってもらい、服として持ち帰る。のちに『カット&ソウン』という名前でプロジェクトにしていくことになる企画ですが、“服をつくること”を通して、体から時間と空間が生み出される瞬間がそこにあり、ファッションを用いて場をつくるところに強く共感し、彼らがこの先に観たいものを私も観たい、と思いました」
当初は会社をつくるつもりはなかったが、想いを共有できる人たちと出会い、結果として会社ができあがり、続けていくことになったそうだ。
「次は何を展示したいのと尋ねたら、『会社を展示したい』と言われて。次の展示品をつくるつもりでサポートしていたら、会社ができていました(笑)。『ファッションがあれば世界は劇場になる』というコンセプトのブランドです。『建物も戯曲もないところに劇場をつくる』とはどういうことか?という自分が考え続けている問いへの解を提示し続けるような気持ちで、そのまま15年間やってきました」
建物も戯曲もないところに劇場をつくる…耳慣れない言葉だが、どういうことだろう。
「演技や戯曲を取り払った後に劇場という仕組みが残ります。『何もないところに劇場をつくる』というのは、そののような構図を生み出して、詩情や物語によって日常を侵食する場をつくるということです。役者でもない普通の人の日常が、服を身にまとうことで、時間や空間が異化される。そうやってファッションで、何もないところに劇場をつくることができると思ったんです」
シアタープロダクツ時代は、そんな想いでファッションイベントを手がけてきた。
「印象に残っているのが、数年前にやった『読むお店』。服のバーコードを読み取ると、レシートとは別にもう一枚紙が出てくる。そこには、読み取ったアイテムに付随した詩が印字されているんです。
このジャケットだからこの詩、というのをあらかじめつくっておいて、買うものの組み合わせで、一人一人違う詩の散文ができあがるようにしました。」
2014年には義足のファッションショー”Rhythm of athletics”を開催した。
「義足をつけたアスリートにご出演いただきましたが、デザイン性の高い義足の美しさもあり、さらに身体能力も高い方々なので、ファッションの可能性を押し広げるような感動がありました。跳躍力もすごかったですし、みなさん素晴らしかったです」
金森さんはシアタープロダクツと共に「ファション」というテーマを持ちながら走り続け、それを通して誰に何を伝えられるか、という根幹を大事にしながら多様な展開に挑戦し続けていた。
ファッションをもっと多様にしたい
ファッションを通じて実験的なコミュニケーションの場を創り続けてきた中で、15年経ち、会社としてのフェーズが変わる中、金森さんもまた、次の場所に行こうとしていた。
彼女はファッションイベントを、シアタープロダクツでのみ手がけてきたわけではない。2009年には建築家とパフォーミングアーツのプロデューサーと金森さんの3人でドリフターズ・インターナショナルを立ち上げ、演劇・ファッション・ダンス・デザイン・建築など異分野の人たちが集まりクリエーションをしていく「ドリフターズ・サマースクール」やその土地や地域という場所と芸術表現との組み合わせで舞台を表現する「スペクタクル・イン・ザ・ファーム」などの事業を展開した。今年は、障がい者や老人など様々な人が出演する「オールライトファッションショー」を実施する。

「ファッションの世界ではどうしても、いわゆる『キレイな女性』という像が固定化していて、ある特定の年齢や体型の人が理想とされることが多い。シアタープロダクツにおいてもブランドとして求めるべき理想のイメージや、事業や商売を考えたときに実際製造できる服の範囲も限られてきていました。
また、シアタープロダクツで行った義足のファッションショーや横浜トリエンナーレ関連企画・ジャパンファッションウィークのイベントとして行った船上のファッションショーなどを通して、アート・パフォーマンス・ファッション・建築・音楽・観光などのさまざま分野の人たちと共に場を作り上げてきたことで見えたものも学んだこともあります。
より多様な幅広い人を対象としたもの作りができる環境を探そうとして、次のステップを探そうと思いました」
マイノリティーとファッションショー
金森さんは今年の春にシアタープロダクツを離れ、キュレーターの田中みゆき氏、自身のNPO、岡山の一般社団法人ひばりエンタテイメントらと「オールライトファッションショー」の準備をしている。
「車椅子の人や障がい者だけでなく、杖をつく人、足が動く人も、動かない人も、年齢、性別に限らず、本当にさまざまな方に出ていただくことになりました。
元々ファッションショーにあこがれていた女の子もいたり、岡山にある生活介護事業所『ぬか つくるとこ』という場所で出会った方々もいたり、ショーに出る理由も出会いもさまざま。参加者の方々へのインタビューを踏まえ、『POTTO』という岡山をベースにしたブランドと、ワークウェアをベースにしたデニムブランド「ジョンブル」ともに、それぞれに合った服をつくっているところです」
今後は、より一人ひとりの多様性に目を向けていきたいという。

「普通の人が持つ個性ってすごくおもしろくて、一枚の布から服をつくるときも、参加者によってディテールが変わることで、全然違うものが生まれます。
確立したクリエイティビティを持っている人だけではなくて、子どもたちも含めて、それぞれの人に宿っているクリエイティビティにもっと目を向けていくことをしていきたい」
アートは問題提起。デザインは課題解決。ファッションは?
金森さんは、ファッションが日用品であること、日常的であることが素晴らしいと思っている。

「展示されているだけの服では、ファッションではなく彫刻作品です。『着ることができる』のが洋服の強み、つまりファッションという形に留まりつつ、でも『問題提起をする』というアート的視点からも見直すことで、服はすごく力を持つと思います」
例えば、今回11月に開催される「オールライトファッションショー」も同じ。
「ファッションが掲げる美しさは多様でいいんじゃないか」という問題提起をもち、株式会社ジョンブルと共に老いや障がいをもつ人たちが実際に装うためにどのような服を作っていくかという行為は課題解決そのものだ。
ファッションによってその両面を合わせることができうるということ、それによってより強い力になるということ。
金森さんが「着る」という服の強みに興味をもち、一人一人の多様性に着目するのは、「何もないところに劇場をつくる」人が、アーティストやデザイナーだけに留まらないからだろう。一人一人の日常があり、その人自身が服を身にまとうことで、人生が照らし出され、日常を異化する場が生まれる。
それはつまり、あなたも私も、劇場という場をつくれるということだ。そう考えると、今着ている服も、それを着ている自分も、いつもとは少し違って見えるかもしれない。
取材場所協力:WRAPPLE wrapping and D.I.Y. +cafe

包装材料卸問屋の株式会社シモジマが渋谷東急ハンズの隣に新業態『ラップル』のカフェをオープン。金森さんはラッピングとDIYをテーマにしたショップの企画に携わった。店頭ではワークショップイベントなどもおこない新しい包装の在り方を来店者と共に創り上げている。
kakite & kikite :菅原沙妃/photo by BrightLogg,Inc./EDIT by PLART & BrightLogg,Inc.

金森香/Kao Kanamori
NPO法人『ドリフターズ・インターナショナル』理事/企画・プロデュース
セントラル セント マーチンズ カレッジ オブ アート アンド デザインの批評芸術学科を卒業後、チンドン屋をへて出版社リトルモアに勤務。2001年にデザイナーの武内昭氏、中西妙佳氏と『シアタープロダクツ』を設立、2017年まで広報ほかコミュニケーションにまつわる企画やマネジメント業務を担当。2010年にはNPO法人『ドリフターズ・インターナショナル』理事に就任。また2012年、包装材料問屋シモジマの新業態『ラップル』のオープンに際し、クリエイティブディレクターを担当。現在も商品企画やブランディングサポートをてがける。