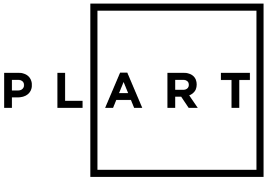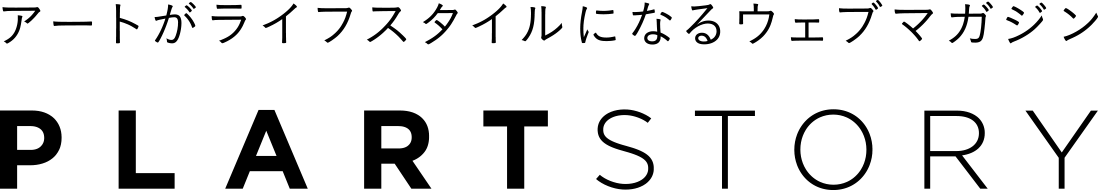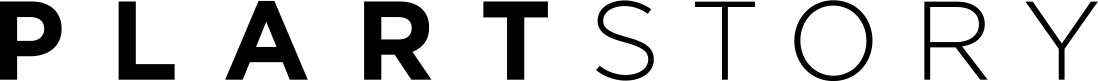【連載】アートとビジネス vol.6「頼もしく、格好よく、素敵に映るような鎧を着る」一般社団法人アート東京 代表理事 來住尚彦


10月15日号
連載「アートとビジネス」とは?
昔から、あこがれのビジネスマンには、アート好きな人が多かった。
その共通点はなんだろう?
それは、「人と違う視点を持っていること」ではなかろうか。
ゼロから生まれてくるアートが好きで、そして、自分も新しい価値を創る。
未開拓のシーンに挑戦するビジネスマンに憧れを持ち、少しでも近づきたくて、僕らは働く。
その人にはなれないけど、アートを通して同じ視点を取り入れる事は出来るかも?
アートには「新しい価値を生み出すヒント」がきっと、あるから。
品川区の臨海部に位置する、天王洲。元々は倉庫街として流通を支えたエリアだが、産業構造の変化にあわせた都市開発により、近年は文化やアートの発信地として存在感を放っている。
その一角にあるTERRADA ART COMPLEXも、一見すると工業地帯にあるただの倉庫だが、エレベーターで上がってみれば、あるフロアはアーティストのスタジオとなり、あるフロアは現代アートを扱うギャラリーが集まっている。「Asian Art Award 2017 supported by Warehouse TERRADAファイナリスト展」(会期:2017年9月23 日〜10月29日)の会場も、先日までは倉庫として利用されていたという。
この展覧会は、「Asian Art Award supported by Warehouse TERRADA(以下Asian Art Award または AAA)」という国際的な活躍が期待されるアーティストを支援するために設立されたアワードのファイナリスト5組を紹介するものだ。AAAを主催する、一般社団法人アート東京の代表理事である來住尚彦(きしなおひこ)さんは、2005年に始まった日本最大級のアートの見本市「アートフェア東京(AFT)」のエグゼクティブ・プロデューサーも、2015年より務めている。
インタビュー前のスチール撮影では、カメラに臆することなくポーズを決め、展示会場を歩けばスタッフ一同に気さくに言葉をかける。アート業界で肩書をもつ人のイメージとは少し違い、見た目も物腰も“理事”っぽくない。來住さんはなぜこの業界にいるのだろう。アートの世界で何をしている人なのだろう。

取材前に、カメラマンの要望に応えてポージングをしてくれた。
なんにでも挑戦して、なんでもできるようになった
早稲田大学理工学部を卒業後、エンジニアとしてTBSに入局した來住さん。「1年目は、エンジニアとして現場にいて、音響機器を片付けながら除夜の鐘を聞きました」というが、周囲に「音楽番組をやる」「音楽ディレクターになる」と宣言し続け、念願叶ってラジオの音楽番組を担当するようになる。
デビューしたての男性アイドルグループのステージにも関わるようになると、まず「エンタテイメントとは?」を知るべくウォルト・ディズニーの本を読み漁った。照明技術の勉強のためなら、他局の音楽番組のスタジオにも毎週足を運んだ。
「人を好き勝手に動かせるのは、神様だけ。でもディレクターは、ステージ上でなら神様。人を好きに動かすことができる。『君はここにいろ。ここから動くな』と言えばそれは絶対」
一方で、神様である以上、ディレクターはステージ上のすべてをこなさねばならない。來住さんは、ステージングを学ぶために、自ら週3回、出社前にダンスレッスンにも通った。まずは何でも自分でやった。1年間で300本のコンサートを観る生活を2年間続けた。音楽ディレクターとしてのキャリアを重ね、アイドルグループはその後、国民的人気を得るまでに成長した。
その中で気がついたのは、会場・施設の使いづらさだった。ディレクターやアーティストが「こんなステージを見せたい」と思っても、それを叶えられる施設がないのだ。
「だったらそれを、俺が創ろう」
TBSテレビのライブハウス「赤坂BLITZ(ブリッツ)」の立ち上げに関わったのも自然な流れだった。支配人も経験した後、今度は赤坂の再開発プロジェクトを任された。赤坂というひとつの町のプロデュースを手掛け、エンターテイメント複合施設として人気を誇る、赤坂サカスを世に送り出した。
振り返れば赤坂BLITZの立ち上げが、プロデュース業に進むきっかけとなった。
ステージ上の人を動かすのがディレクターの仕事だが、プロデューサーは、人を動かすだけでなく、人と人をくっつけることも仕事。ステージの外にも目を向け、お金を集めることも考えなくてはならないし、プロモーションにも関わらないといけない。ディレクターとプロデューサーではやることも、求められる能力もまるで違う。

アートフェア東京2017オープニングパーティーにて、ファッションデザイナーのコシノジュンコ氏がVRアートパフォーマンスを行った。
そこに不安はなかったのだろうか。すると來住さんは、今やカリスマ的存在の女性アーティストの名前を挙げた。
「デビューしたての頃から、彼女はものすごく魅力的だった。でも僕はその魅力を言葉で説明できませんでした。すると事務所の社長さんが教えてくたんです。『あの子は歌える。ダンスもできる。スタイルもファッションセンスもいい。だけど、どれも一流ではない。けれど4つできることが素晴らしい』と。僕は、演出ができます。プレゼンでお金を集めるセールスの能力もある。人や場所のキャスティングもできる。自分の周りには、それぞれ分野に秀でた方はたくさんいましたが、全部やる人は他にいない。でも僕はできる。だからプロデューサーになろうと決めたんです」
開けたアートの世界への入り口となった『アートフェア東京』
ビジネスの目線でアート業界に触れたのは、興味や関心よりも先に「使命だった」と來住さんは振り返る。
赤坂サカスでコンテンポラリーアートフェアを、という話が出て、來住さんはイギリスで毎年開催される現代アートフェア「フリーズ・ロンドン(Frieze London)」を訪れる機会を得た。そこで音楽の世界との客層の違いを知るとともに、アートの可能性を感じて、日本のアートがもっと世界に羽ばたけるという確信を得た。

2017年10月5日〜8日にリージェンツ・パークで行われた、Frieze London 2017の様子。(https://www.flickr.com/photos/friezepress/sets/より)
アートフェア東京のプロデューサーとして声がかかったのは2012年ごろだった。
「音楽をやっていたら、ベニュー(施設)を造ることになったり、赤坂という町を創ることになったりした。急に京都の伝統産業を守るプロジェクトが決まったこともある。プロデュースを仕事にしていると、色々なお話をいただきます。『アートフェア東京』のお話をいただいた時も驚きはしませんでした」
感性を磨いてモノサシを決め、いざアート業界へ
「タイミングが合うという事は、それが必然だと思った。そして何より面白そうだったから」
アートフェア東京のエグゼクティブ・プロデューサーを引き受けた理由をそう語る。「面白い」の根拠を尋ねたところ、テレビ業界で学んだ『視聴者は半年遅れる』という考え方を教えてくれた。
「今、創り手の僕たちが飽きたなと思ったら、一般カスタマーも半年以内に番組に飽きる。その前に新番組を用意しないといけないという考え方がありました。この『半年』という単位は絶対ではないから、時代が変われば一般カスタマーの飽きるスピードも変わるかもしれない」
「自分の感性が衰えれば、半年ではなく明日にでも世の中に飽きられるかもしれない。けれど、少なくともそうならないよう努力は続けてきました。感性を磨き、情報を集め、意識的にも無意識的にも多くを蓄積して」

自分が飽きていないか、面白いと思えているかの基準を「自分の中のモノサシ」に決め、そしてアート業界に踏み出した。
中学生の時に「みんなが幸せになる方法」を考えた
努力を怠らず、経験を積み重ね今に至る。その堅実なスタイルからのイメージと、目の前にいる來住さんとは、面白いほどイメージが重ならない。社会人になる前は、一体どんな人だったのだろう。
「責任感はあるけれど、おっちょこちょいだと言われました。おっちょこちょいというのが、軽いという意味だったのかなと今では思います。大学に入る頃から女の子に『軽いよね』と、社会人になると『仕事はできるけれど、軽いよな』と言われるようになったので(笑)」
そして「昔の話で、今は違いますが。たまたまですが」と断りを重ねた上で、「モテたんです」と切り出した。
「中学校に上がると、クラスの女の子全員が僕を好きだというくらいにモテました。そんな時、ある女の子と親しくしたことがきっかけで、女の子同士の喧嘩が始まってしまったんです。大変なことをしてしまったとショックでした」
「どこにどれだけ愛情を注ぐのか、真剣に悩みました。僕のことを好きだと言ってくれるみんなが、どうすると平和か。どうすると幸せか。かっこよすぎますが、中学生なりに真面目に考えました。そして、デートをするなら全員とするか誰ともしないか。0か100かだと思い至ったんです。バカらしいと言う人もいると思いますが、真剣でした」
誰に対しても重くならない、“軽い來住くん”に至ったプロセスに、思わず感心させられた。そしてはからずも、プライベートでのアートの接し方にも当時の影響を垣間見ることができた。
來住さんの自宅には、自分で買った作品は飾られていないのだという。飾ってあるのは、アーティストやギャラリストから贈られた作品ばかりだ。

「次々に入れ替えて飾っています。ひとつの作品だけを長く飾ることもしません。これは前の業界にいる時からのポリシーですが、プロデューサーは『このアーティストが好き』と言ってはいけないと思うからです。ディレクターやキュレーターは、アーティストに入れ込んでいい。アート業界には、贔屓(ひいき)のアーティストに入り込める方はたくさんいます。そのなかで必要なのは、入れ込まずにプロデュースできる人間だと思います」
どうするとみんなが幸せか。どうすると平和か。クラスの女の子たちのために行き着いた愛のある「軽さ」と、現在の來住さんのアート業界との向かい方の間に、繋がりを見た気がした。
“來住尚彦”という鎧が頼もしく、格好よく、素敵に見えたら嬉しい
贈られた作品だけを部屋に飾るのには、もうひとつ理由がある。
「ギャラリーやアーティストの方々は『來住さんにはこれがいい』と見立てた作品を贈ってくださいます。それを飾っておくことで“期待通りの來住さん”でいたいんです」
フラットな目線で、フェアな立場を、そしてバランスをとり続ける。さらに周りに求められる來住さんであり続ける。あるとき、講師を務めた大学でこんな質問を受けたという。
―そういう自分に、疲れませんか?
学生らしい直球の質問に驚いた。しかし隠すことなくこう答えた。
「疲れているかもしれないけれど、わからない。なぜなら本当の僕はこうじゃないから。本当の僕なら疲れたり、傷ついたりするかもしれない。けれど”鎧”を着ているから大丈夫」
來住さんの思い描く”鎧”は、中世ヨーロッパにみるタイプの鎧ではなく、戦国武将が着る甲冑のような鎧姿だ。身を守るだけでなく、華やかさと強さのシンボルであり、戦場の味方の士気を高める鎧兜。決してネガティブな意味合いのものではない。
「『こういう自分であろう』という思いで、誰もがコスチュームデザインを創っているはずです。目指した自分になるよう創ることは、嘘をつくことにもなりませんし、それこそが大人になるということだと。僕の場合、今の自分が“來住尚彦”という鎧です。この姿がみんなの目に、頼もしく、格好よく、素敵に映るなら素晴らしいことだと思っています」
「求められる自分」でいること。
美大・芸大生や若手アーティストたちに繰り返しかけてきた言葉がある。
「金のためには動くな。でも、金持ちにはなれ」
アーティストが経済的に裕福になるには、教育機関が担うEducation(教育)だけでなく、その後の世界で育ち生き抜くためのProduce(作品のクリエイティビティ)やPromotion(宣伝・広告)が必要だという。しかし大学は、あくまでもEducationの場。卒業したその先をみてやる誰かがいなければならない。
「だったら、俺が面倒みるよ」
そして2017年、アート東京はAsian Art Awardを立ち上げた。現代アートの分野で活躍を期待されるアーティストを支援するアワードだ。スポンサーをみつけ、日本だけでなく中国とシンガポールからも招いた審査委員会を構成し、5組のファイナリストたちにシンガポールと東京で発表のチャンスを与えた。

AFT2017開催セレモニーの様子。

AAA2017 ファイナリスト、審査員、選考委員、主催、特別協賛の集合写真
「若いアーティストたちを金持ちにしてあげよう、と真面目に考えられる人が、もっともっと増えるといい。金持ちになることは、周りよりちょっとだけ先を走るということ。みんなの先を走ってその背中をみせてほしい。みんなから頼られるようになってほしい」

そして誰かに頼られたときは、「だったら、俺がやるよ」と言ってほしい。
日本のアートがオリンピック後も輝くために
2020年の東京オリンピックが終わると、訪日外国人の数もピークを越え、共通の目標も失って、日本は少し寂しい時代になるかもしれない。だからこそ來住さんは、その先を見据える。
「2019年の今頃までに、2025年から2030年までのプランを立ち上げていきたいです。アートをベースにした万博かもしれないし、IR(統合型リゾート)かもしれない。その時には、日本中がアートで輝く都市であってほしい」
そしてふと、明治神宮で和楽器による野外コンサートを開催した時のことを思い出す。
月明りの中、尺八の長音とともに雲が流れた。琵琶の音に応えるように、かがり火がパチパチと弾けた。琴の音と風の音が重なりあった夜、日本には世界に誇る美しい文化があり「僕らは花鳥風月の中にいる」と感じた。
「アートや工芸、音楽など、各分野がそれぞれに力を持ち、世界で認められるようになってほしい。その時に、そのベースには日本の文化があると伝わるようになれば素敵ですね。まずはそんな未来を一緒に目指す仲間を増やしていきたいです」
インタビューで伺ったとおりならば、この日お会いした來住さんも鎧兜を装備していたことになる。そうだとしても來住さんは、華やかで晴れやかで、軽やかだった。その鎧姿でアート業界を舞台に、どんな立ち廻りをみせてくれるのか。想像するとワクワクしてくる。
kakite : 塚田史香/photo by 林ユバ/EDIT by PLART(松本麻美)

來住尚彦/Naohiko Kishi
一般社団法人 アート東京 代表理事
アートフェア東京 エグゼクティブ プロデューサー
2015年5月一般社団法人 アート東京 設立。日本のアートマーケットの発展と芸術文化の振興を目的とし、アートを軸に様々な事業を企画、制作する。
1985年、株式会社TBSテレビ入社。コンプレックスライブ空間「赤坂BLITZ」(1996年)を企画立案し、支配人に就任。赤坂サカス推進部部長として、エンターテイメント施設と都市の共生をテーマに、複合エンターテイメント空間「赤坂サカス」(2008年)の企画立案、プロデュースを行う。様々なテレビ番組や舞台、イベント、コンサート、音楽ソフトのプロデューサー、演出家として活動する他、地方自治体や行政機関のブランディング、企画プロデュースを多数手がける。また、京都大学を含む教育機関や自治体等で、講演活動を行う。
2015年より、現職として国内最大級の国際的アート見本市「アートフェア東京」を主催し、内閣府を始め、外務省、経済産業省、文化庁、観光庁、各自治体及び駐日各国大使館と連携し、芸術文化を通じた国際交流の場を創出。多くのメディアを巻き込み、国内外に広く情報発信するなど、日本のアートシーンの発展に寄与するとともに、アートを軸に分野横断的で国際的な交流を生み出す活動を行う。2016年より「日本のアート産業に関する市場調査」をアート東京として実施。アートを切り口に地域の魅力を外国人に紹介する「アートツーリズム事業」実施、地方創生に貢献。2017年には、文化庁の助成事業、平成29年度戦略的芸術文化創造推進事業「美術分野における地方発以上拡大等の取組に関する企画運営業務」企画案選定委員会委員を務めるなど、芸術文化の拡充に寄与している。
取材時のオフショットと、Asian Art Award 2017ファイナリスト展の様子



AAA2017 大賞 山城知佳子 《土の人》(2017年 劇場版)展示風景。
cooperation AICHITRIENNALE 2016 | ©Chikako Yamashiro, Courtesy of Yumiko Chiba Associates

AAA2017 山本高之《Lie to Me》(2017年)展示風景。