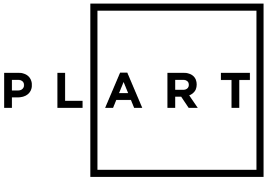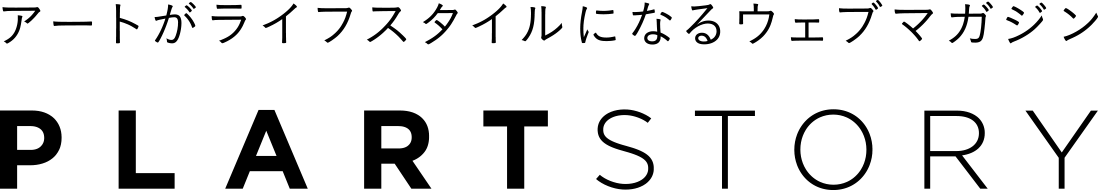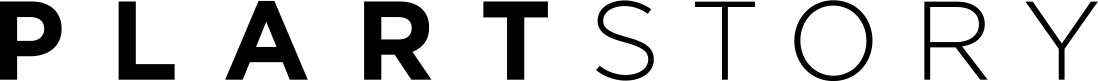能の本質は「想像すること」。誰も傍観者ではいられない【能×現代音楽アーティスト 青木涼子】


3月15日号
アートを傍観者としてただ享受しようという姿勢は、もしかしたら間違っているのかもしれない。能×現代音楽アーティスト・青木涼子さんの話を伺って、そんなことを考えた。
女性であることと能の家の出身でないこと。ふたつのハンディキャップを抱えながら、伝統芸能である能の新たな可能性を模索し続ける青木さん。2010年から取り組んでいる、能と現代音楽を融合させる試みは、日本国内のみならず海外でも高い評価を受けている。とはいえ、これまでの道のりは「苦労ばかりだった」と語る彼女。それでも能という表現方法を選び続ける原動力はどんなところにあるのだろうか。
日本の芸術ってカッコいい! バレエ少女が能に目覚めた理由

── まず、青木さんが能を始めたきっかけについて教えてください。
根源的なきっかけになっているのは、8歳のときにクラシックバレエを習い始めたことです。そこから、パフォーミングアーツの世界にのめり込んでいったので。
── クラシックバレエを習いたいと思ったのはどうしてだったんですか?
『ハーイ!まりちゃん』という漫画のなかで主人公がバレエをやっていて。それを見て自分もやりたいと思ったんです。その後中学3年生まで、約8年間習い続けました。
── 西洋の芸術であるクラシックバレエを習っているなかで、日本の伝統芸能である能に興味をもったのにはどんな経緯があるんですか?
小学生のとき、建築家の父が寺院の設計をすることになって。その事前準備のために、家族で奈良のお寺を回ったんです。はじめは「なんてつまらなさそうな旅行だろう……」と思っていたんですが、実際に足を運んでみると、スケールの大きさや空気感、建築の素晴らしさに圧倒されて。そのとき「日本のものってカッコいい!」という気持ちが芽生えました。
── なるほど。でも、その経験があってすぐ能を始めたわけではないですよね。
そのころ一度、母と一緒に能の鑑賞に出かけたことがあったんですが、まったくおもしろさがわからず……。ただパフォーミングアーツ自体は好きだったので、日本の舞台芸術のひとつとして、歌舞伎や日本舞踊と合わせて興味は持っていました。
── それが少し疑問だったんですが、日本の舞台芸術に女性が挑戦するとしたら、もともと男女問わず門戸の広い日本舞踊という選択肢が一般的な気がして。なぜ、あえて能を選んだんですか?
中学2年生のときにテレビで能の鑑賞入門の番組がやっていたんですね。そのとき、流れてくるお囃子の音に合わせて、今にも動き出したい気持ちになって。派手でリズミカルな演目だったこともあるんですが、自分もこの音に合わせて舞を舞いたいという思いを強く感じました。それで、カルチャースクールに通って能を習い始めました。
── それでは、能が男性の舞台芸術として発展してきたという背景はあまり意識していなかった、と。
はい。先生が女性だったこともあって、習い始めた当初は能の世界がここまで男性社会であることを知らなかったんです。
── 実際に能を習いはじめて、率直にどう感じましたか?
舞を舞いたくて習いはじめたものの、能の基本は謡(※1)だと教わって。ちょっと思ってたのと違うぞ、と(笑)
※1 謡(うたい):能の歌謡部分。言葉やセリフのこと。
── 青木さんはいち早く舞が舞いたかったんですもんね。期待と違う内容だったのに、辞めずに続けたのはなぜだったんでしょう?
地元の大分市には市営の能楽堂があって、カルチャースクールの稽古でも使わせてもらえたんです。檜舞台のにおいや能楽堂特有の空気感のなかにいると、気分がものすごく高揚して。なんだかちょっと上手くなったような気もするし。それが楽しくて続けていました。
── 能と並行してバレエも続けていたわけですよね。パフォーミングアーツというジャンルは同じですが、なぜ最終的に能を選んだんですか?
中学3年生のとき、ロシアのワガノワ・バレエ・アカデミーにほんの少しですが短期留学をしたんです。記念で行ったくらいだったのですが、正規の生徒たちのレッスン見学をさせてもらったら、レベルの高さに圧倒されてしまって。「日本のただのバレエ・スクールで、どう頑張ってもこの人たちのことは超えられない」と実感してバレエをやめました。
── それで大学進学の際は、能で芸大に進んだんですね。
中3でバレエを諦めて、高校に入学したばかりのころは一般の大学に進学するつもりでした。でも私はやっぱりアートが大好きで。進路を決めるころには、芸大に進学してたくさんのアーティストたちに出会いたいと思うようになっていました。そうしたらなんと、能で芸大が受験できるって言うじゃないですか! これはやるしかないぞ、と。だからはじめは、能を学びたいというよりは、芸大に進学するための手段として考えていました。
── そして芸大の能楽専攻に進学された、と。実際、芸大に入学してみてどうでしたか?
それが、またしても期待を裏切られたんです(笑) 次世代を担うアーティストたちに出会えると思って芸大に入ったのに、そのころの能楽専攻はかなり閉鎖的な雰囲気で。毎日、同じ専攻の人にしか会わないんです。もともと能の家の出身の生徒も多かったので、特殊な環境でした。
── そんななかで青木さんは、女性であるうえに能の家の出身ではない。ハンディキャップが大きいぶん、苦労が多そうです。
うん、苦労ばっかりです(笑) 大分にいたころはただ楽しく続けていたんですが、大学に入ってから「女性であること」と「能の家の出身ではないこと」が、能の世界でどれだけ不利なことか実感しました。
新しいものを生み出したいという欲求から、現代音楽とのコラボレーションへ

── 大きなハンディキャップを抱えるなかで、それでも能を続けていこうと思った理由はどこにあるんですか?
私が学生のとき、ちょうど能楽専攻のなかでも横のつながりを作っていこうとしていた時期だったんですね。担当教授が、家のしがらみがないぶん自由にやってみなさいと背中を押してくれたこともあって、オペラ科や作曲科と一緒に作品をつくる機会を得ることができました。私はもともと、何か新しいものを生み出したいという欲求が強かったんですが、能をはじめとする伝統芸能の世界は守っていくことが正義。自分の欲求を満たすことは不可能だと思っていたときに貴重な機会を得られたのでラッキーでした。
── 学生時代のコラボレーションが現在の能と現代音楽の融合という試みにつながっている、と。
実は、そのコラボレーションを通して見えた課題がたくさんあったんです。それまで能がほかの芸術とコラボレーションするときは、独特な雰囲気だけを求められることが多くて。たとえば「曲を作曲したから合わせて舞を舞ってください」っていうような。でもそれはすごく表面的で、能の本質をとらえていないんです。
── と、いうと?
私がそれまでずっと言われ続けてきたのは「能は謡こそが大切だ」ということ。
能って、日本舞踊やバレエと比べると、動きの語彙がとてつもなく少ないんです。限られた動きだけで、抽象的なものから具体的なものまでを表現しなければならないんですが、そこに意味を与えるのはすべて謡。謡と舞が合わさってはじめて情景や物語が理解できるものだから、ただ音楽に舞をつけたところで空白になってしまうだけ。そう考えたとき、新しい能を模索するにはまず謡を含めた音楽部分を新しくしないといけないと気付きました。
── なるほど。能の音楽を新しくしていくために、具体的にどんな取り組みを行ったんですか?
2010年から、現代音楽の作曲家に声を掛けて新しい謡のための音楽を作ってもらうという試みを行っていました。それも、ただ好きなように作曲すればいいわけではなくて、自分がどんな部分に能の要素を取り入れたのか、プレゼンテーションをしてもらいました。そして曲を発表し、その後お客様とディスカッションを行いました。そのなかで徐々に「これはおもしろいかも」と感じられるものが増えていきました。

2016年 ステファノ・ジェルヴァゾーニ作曲「夜の響き、山の中より」
青木涼子、ディオティマ弦楽四重奏団
Photo : Hiroaki Seo
── 単純な疑問なんですが、謡を”作曲”することって本当にできるんですか? そもそも謡には音程や音階という概念は存在しないですよね。
そうなんです。そのうえ、リズムもピッチも安定させなくていいのが謡なので。難しいことをやっているのはわかっていました。そこで、作曲家のために謡のいろはを解説したウェブサイトを作りました。私の声の音程を相対的に五線譜に落とし込んだり、節(※2)の法則を音階で表したり、西洋音楽の下地を持った人たちがなるべく理解しやすいような工夫はしています。 作曲家のための謡の手引き
※2 節(ふし):謡を構成するひとつの要素。言葉の節回しを表している
── とはいえ、満足のいくものができるまでは時間がかかりそうですが……。
最初の3年間はずっと模索し続けていました。私はリズムもピッチも取るのが得意でないので、作曲家にしてみたら、とんでもなく不自由な楽器を渡されたような気持ちだったでしょうね。それに、今までにない新しい発想で、能を自分の音楽の中に取り込んで、曲を作ってほしかったから、能について知識や素養がある作曲家にはあえて声をかけなかったんです。ものすごくチャレンジングな試みでしたが、2曲、3曲と繰り返し作曲していくうちに、何かを掴んでくれるようで。時間はかかりますが、この積み重ねが重要なんです。
発想の転換が自分の存在に価値を与えてくれた

── 何度か「女性であること」がハンディキャップになったという話が出てきましたが、女性と能の関係性について何か考えていることはありますか?
私、そのテーマで博士論文を執筆したんですが、なかなか簡単には踏み込めない部分なんです。能は成立した室町時代初期は「猿楽」と呼ばれていて、男女問わず舞台に立てるものでした。女性が舞台に立てなくなったのは、江戸時代に幕府の命で禁止されたため。そこから男性原理の世界になっていくわけです。
── 舞台に立つことを禁止されていた女性が、能の世界に舞い戻るのにはいったいどんな経緯があったんでしょう?
明治維新後、能楽師はパトロンの後ろ盾に頼って生計を立てていきます。すると、その家の娘に稽古をつけてほしいと頼まれるようになる。つまり、お嬢様の習い事として女性がまた能に触れるようになったんです。でも、女性能楽師が正式に認められるのはもっとずっと後、第二次世界大戦後のことでした。
── ということは、女性能楽師の存在は公に認められているわけですよね。そのなかで「女性であること」がハンディキャップになるのはなぜなんですか?
発展する過程で「男性の芸術」として確立してしまったので、いまだにすべてが男性基準の世界なんです。たとえば、能では別のものに変身するとき能面をかけるので、男性が男の役を演じるときは素顔のまま。女の役を演じるとき女面をかけます。それじゃあ、女性が女の役を演じるときは素顔のままでいいのかというと、それは様式と違うから通用しないんです。
── なるほど。合理性よりも様式が優先される、と。
ほかにも装束の着付けも、美しさの評価もすべて男性基準。だから女性が能を演じるときのほめ言葉が「女に見えなかった」とか「男みたいだった」ということになる。ということは、どう頑張っても「男性以上」にはなれないわけです。本当にそれでいいのかなって。
── だからこそ青木さんは新しい能の可能性に賭けたわけですね。
男性原理の能の世界のなかで、葛藤している女性能楽師の方もたくさんいて。能の家の出身の女性は「男にさえ生まれていれば」と、とくに辛いかもしれません。そのなかで私は、家のしがらみがなかったおかげもあって発想の転換ができました。能の世界では圧倒的に不利だった自分が、現代音楽のフィールドに移ったら、新しい価値を生み出すことができた。視点を変えてみるってすごく大切なことだなと、改めて思います。
アートはただ享受するのではなく、自分から働きかけていくもの

2015年
Hakuju Hall アートXアートXアート
〈能X現代音楽Xファッション〉
Photo : Junichi Takahashi
── 能に対する一般的なイメージは「難しい」「理解できない」というものが大半だと思います。その現状について思うことはありますか?
能の本質って「想像すること」なんです。能は、謡と舞、そして囃子とが合わさってひとつの作品を作り上げています。古語で綴られる物語、動作が表しているもの、音の表現……とすべての要素を理解した瞬間、そこに情景や物語がパッと浮かび上がってくるから楽しい、インテレクチュアルな芸術なんです。
── つまり、ある程度の知識や素養がないと本質を理解するのは難しい、と。
というより、知れば知るほど見え方が変わる、それを楽しむのが本質なんじゃないかと。そういう部分は現代音楽とも通ずるところがあります。今っていろいろなものがただ享受される時代だから、すぐに理解できて楽しめるものばかりが求められてしまうけど、それは本来のアートとの向き合い方とは違う気がします。
── と、いうと?
アートはエンターテイメントと違って、ただ楽しむためのものではありません。アーティストというのは人の人生や社会情勢になにか変化をもたらしたいという衝動が、創作の原動力になっているはずなんです。だから楽しむことだけが必ずしも正解じゃない。違和感や怒りといった負の感情を感じさせるものだってある。アートの本質を理解するためには、自分から働きかけていくことが必要なのではないでしょうか。
── たしかに、受け手側のなかでアートとエンターテイメントの境が曖昧になってしまっている気がします。最後に、青木さんが今後目指していきたいことを教えてください。
能のようなパフォーミングアーツって、本来は一瞬で消えてなくなってしまうものなんです。それが最近動画が主流になってきたことで、生で観て体感することの価値が伝わりにくくなっていて。でも生でしか感じられない熱とか空気感がパフォーミングアーツの本質。だからいろいろな人に足を運んでもらえるように、新しい試みや挑戦をどんどん続けていきたいです。
アートと向かい合ったとき、ただの傍観者ではいられない
青木さんの言うように、現代人は容易に理解できないものに対して無関心になりがちだ。でも「わからないから、知りたい」というのは、人間の根源的な欲求のように思う。本当の意味でアートと向かい合いたいのなら、ただの傍観者ではいられない。自分から働きかけていく姿勢を、忘れてはならないだろう。
kakite & kikite : 近藤世菜 / photo by Hiroyuki Otaki /EDIT by:PLART & BrightLogg,Inc.
衣装協力:YASUTOSHI EZUMI (http://www.yasutoshiezumi.com/)
<公演情報> 青木涼子 能 × 現代音楽
青木さん「能と衣装と音楽の三位一体を目指した作品を上演します。衣装はリトゥンアフターワーズというブランドの山縣良和さんが手がけてくださいました。布団に80年代アイドルの刺繍が施されていて、とてもエッジーな仕上がりです。さらに、衣装に取り付けた携帯電話を使って曲を演奏するシーンもあります。即興的に音を鳴らすのではなく、作曲家の馬場法子さんが楽譜に書いたものを演奏します。攻めの姿勢あふれる作品をアートに昇華させることができたので、ぜひたくさんの方にお越しいただきたいです!」
開催日:2017年5月20日(日)15:00開演
会場:浦安音楽ホール ハーモニーホール
チケット:(全席指定)¥3,000
【一般発売日:4月2日(日)】【友の会先行予約期間:3月21日(火)~3月22日(水)】

青木涼子(あおき りょうこ)
東京藝術大学音楽学部邦楽科能楽専攻卒業(観世流シテ方専攻)。東京藝術大学音楽研究科修士課程修了。ロンドン大学博士課程修了。博士号(Ph.D)取得。世界の主要な作曲家と共同で、能と現代音楽の新たな試みを行っている。2014年CD「能×現代音楽」リリース。世界各地の音楽祭に多数招待されている。2013年マドリッド、テアトロ・レアル王立劇場にG・モルティエのキャスティングのもと、W・リーム作曲オペラ《メキシコの征服》マリンチェ役で好演。平成27年度文化庁文化交流使。あいちトリエンナーレ2016参加アーティスト。2017年春の三越伊勢丹JAPAN SENSESのメインヴィジュアルに起用。 http://ryokoaoki.net